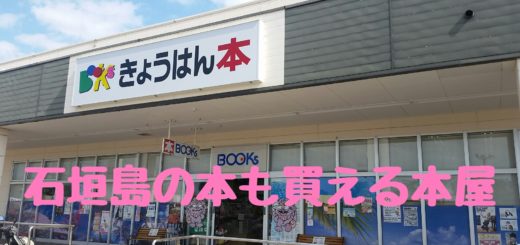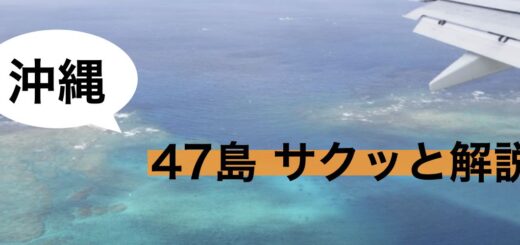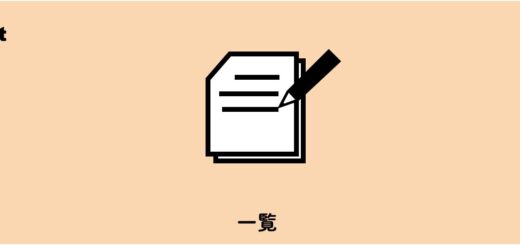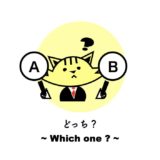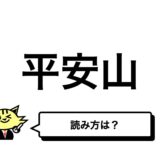石垣島|お守り
![]()
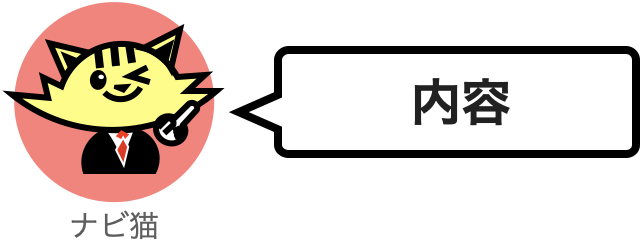
石垣島のお守りについての紹介です
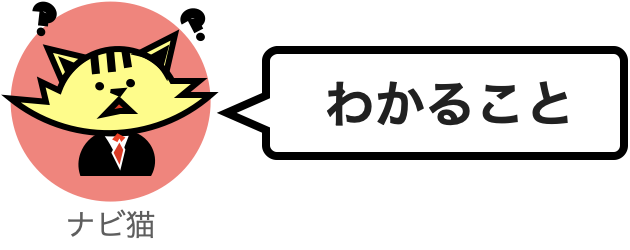
- 石垣島で買えるお守り
目次
石垣島|お守り

石垣島にあるお寺「桃林寺」では、お守りを買うことができます。
また、お土産屋でも「マース袋」というお守りが販売されています。
- 桃林寺のお守り
- マース袋
桃林寺のお守り

石垣島の桃林寺では、お守りを買うことができます。
毎年、正月ごろになると境内の一角に、お守りケースが設置されます。

桃林寺のお守りケース(販売所)
桃林寺のお守りケースからお守りを選び、書いてある金額だけ賽銭箱に入れる仕組みです。
いつでも買えるわけではありませんが、お守りケースが設置されていたら、購入してみましょう。
桃林寺のお守りには「石垣島桃林寺」の刺繍がしてあるので、お土産にもおすすめです。
マース袋

マース袋は、石垣島のお土産屋で買えるお守りです。
マースとは?
マースは沖縄の方言で「塩」を意味しています。スーパーなどに行くと「シママース(島マース)」という名前で塩が売られています。調味料としても使われる塩ですが、身を清めたりする時にも使われます。
沖縄では、魔除け、厄除け、交通安全祈願などにも「塩(マース)」が使われます。
マース袋の由来
沖縄が琉球王朝だった時代から、塩はお守りとして持ち歩かれていました。旅人は特に小袋に塩を入れて、道中の安全を祈願したそうです。
想像ですが…
旅人がお守りとして「塩」を持ち歩いていたっていうことを聞いて、初めに思い浮かんだことがあります。それは、道に迷った時、最悪の場合に舐めて「ミネラル補給」になるなと思いました。
沖縄では山の中に食べれる植物がたくさん生えているので、知っていれば命をつなぐことができる。ですが、塩分は取りずらいので「塩」にした。なんてことがあったのかもです。
「マース袋」が買える場所
マース袋はおみやげ屋さんに売っています。自分が購入したのは「いしがきいちば」。いしがきいちば には伝統的な織物「ミンサー織り」の袋や、紅型(びんがた)の袋も売られています。オリジナルのマース袋を作って贈るってのもいいですね。
関連記事>>>ユーグレナモール<おみやげ>まとめて買うなら「いしがきいちば」がお得
「いしがきいちば」について
【アクセス】離島ターミナルから約600m
【路線バス】全系統「バスターミナル」下車、徒歩10分
【おすすめの時期】通年
【みどころ】送料無料、広い店内、品揃え豊富
【滞在時間】約1時間
【営業時間】9時00分~20時00分(夏季は9時00分~21時00分)
【住所】沖縄県石垣市大川207-1
【電話番号】0980-83-9139