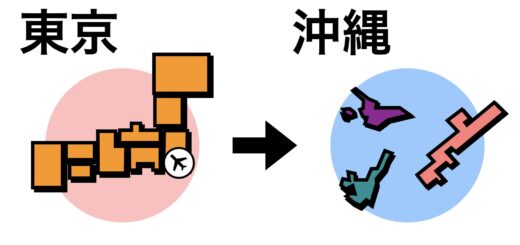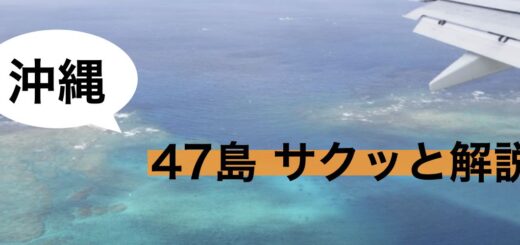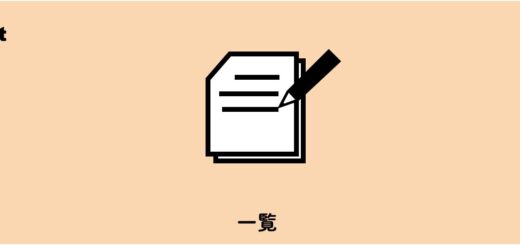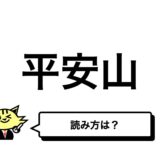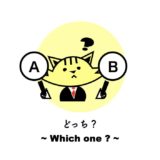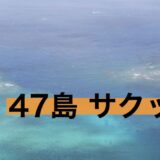沖縄|ヤギ|飼われている理由は?品種・料理・食べてみた感想
![]()

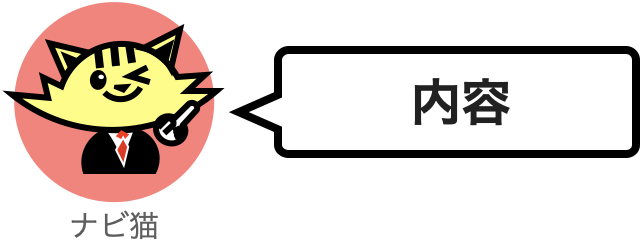
沖縄のヤギについてまとめた記事です
目次
沖縄|ヤギ

沖縄の離島に行くと、必ずと言っていいほど見かけるのが「ヤギ」です。
草むらや道端でも見かける生き物。
白ヤギが多いのですが、たまに黒ヤギも見かけます。
沖縄|ヤギ|飼われている理由

沖縄の島々では、ヤギを飼う習慣があります。
いろんな理由がありますが、ここで一部、紹介していきます。
生命力が強い
ヤギは「飼うのが簡単」「病気になりにくい」「タフ」な動物です。
逃げないように紐で繋いでおきますが、基本、放牧状態。
1週間ほど構わなくても、周りの草を食べて元気に生きています。
草刈り要員として大活躍
また、ヤギは「草刈り要員」としても活躍します。
沖縄は気温が高いので、草が伸びるスピードも早いです。
ヤギは生えている草はもちろん、生えかかりの新芽も食べてくれるので、除草効果も高いです。
食べるため
最後の理由は、食べるためです。
沖縄では「ヤギ汁」「ヤギそば」など、ヤギ料理が提供されています。
島のおじいさんに聞いた話では「1歳半が食べごろ」だそうです。
ヤギの品種

沖縄にもともといたヤギは「黒い色のヤギ」が多かったそうです。
ですが、最近は「白い色のヤギ」の方が多く見かけます。
品種が違う
「黒」と「白」は、ただの色違いではなく『品種』の違いです。
白いヤギは「ザーネン種」といい、大型で短期肥育に向いている種類のヤギ。
1926年に長野県から輸入した「日本ザーネン種」をもとに沖縄のヤギと交配させ、品種改良が行なわれました。
黒ヤギは珍しい
その品種が今に引き継がれ、沖縄には「白いヤギ」が多くなったそうです。
元々いた「黒いヤギ」はほとんど見なくなりましたが、今ではトカラ山羊と呼ばれ「波照間島」「奄美諸島」「トカラ諸島」「屋久島」に、数が少ないですが生息しています。
沖縄|ヤギ料理

最近では日常的に食べられるヤギ料理ですが、以前は、お祝い事があると食べるご馳走でした。
家で食べることが多かったヤギですが、近年では「ヤギ料理専門店」などで食べることが一般的。
ヤギ料理専門店では、次のようなメニューが販売されています。
ヤギ汁

沖縄の離島では、成人式やお祭りがある「ヤギ汁」を食べることがあります。
独特の匂いがありますが、滋養強壮に良いと言われています。
ヤギそば

沖縄そばの具をヤギ肉にしたのが「ヤギそば」です。
お店によっては「ヤギのホルモン」も一緒に煮込んでいることもあります。
沖縄|ヤギ|買える場所

沖縄では、ヤギのお肉や、ヤギを加工した商品を、スーパーなどで買うことができます。
置いていないスーパーもありますが、置いてある割合は結構高めです。
また、道の駅のような「ファーマーズマーケット」でも販売されていることがあるので、冷凍食品のコーナーをチェックしてみましょう。
近年では、街中にも「冷凍の自動販売機」でもヤギラーメンなどの商品が販売されていたりもします。
沖縄では結構、身近な場所で売っていたりもするので、気になる方はぜひ!
沖縄|ヤギ料理|食べてみた感想

ここからは、実際に「ヤギ汁」を食べてみた感想です。
ヤギ料理は気になるけど、どんな感じなのか知りたい方は読み進めてみてください。
肉の味が濃い
ヤギ肉は、肉の味が濃く感じます。
レトルトパックだと、しっかりと煮込まれているので柔らかく食べられました。
独特の匂いがある
ヤギ肉には、ヤギ特有の匂いがあります。
お店によっては匂い消しの工夫がされているお店もあり、匂いが弱めなお店もあり。
「フーチバー(よもぎ)」を入れると、ヨモギの香りでヤギの匂いが気にならなくなります。
脂が多め
ヤギ汁は、脂が多めでした。
脂が多めですが個人的には、結構、さっぱりと食べられました。
パックのまま温めるのがおすすめ
ご家庭でレトルトパックを温める際は、レトルトカレーのようにパックを開封せずお湯に入れて温めるのがおすすめです。
パックを開け、冷たいヤギ汁を鍋に入れて火にかけたら、温まるまでに部屋にヤギの匂いが充満し大変でした。くれぐれもご注意ください。
沖縄|ヤギ|関連記事
島から探す|関連記事
トップページ