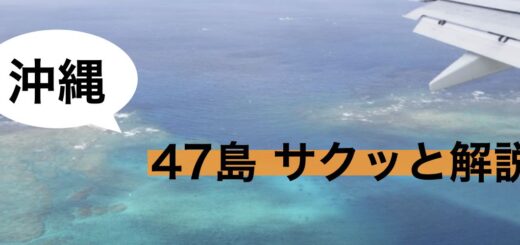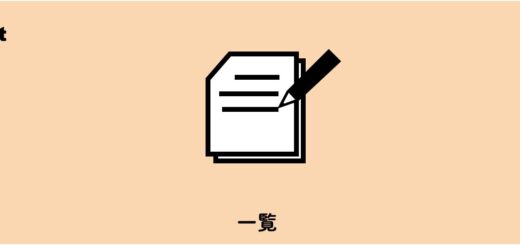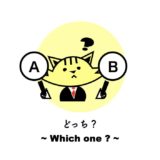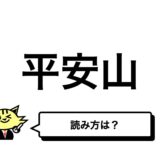沖縄そば
![]()
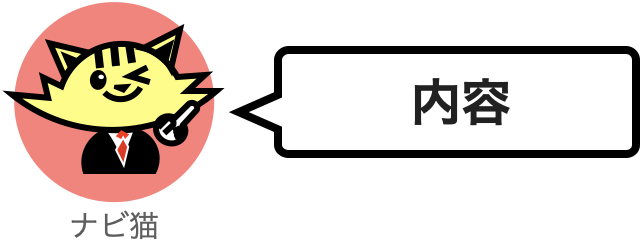
沖縄そばをまとめた記事です
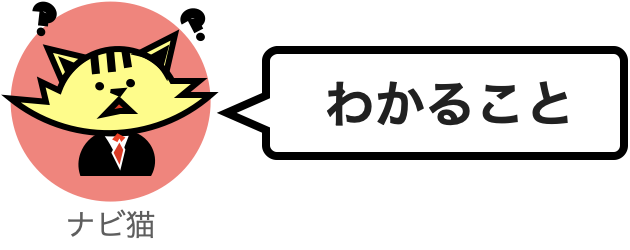
- 沖縄そばとは
- 沖縄そばの種類
- 沖縄そばのメニュー
目次
沖縄そば

沖縄そばとは
沖縄そばは、沖縄で食べられている麺類です。
地域によって麺の種類や太さ、スープの味付けが変わります。
沖縄そば|原料
麺の原料は「小麦粉」「かん水」です。
「蕎麦粉」は使用されていません。
沖縄そば|種類
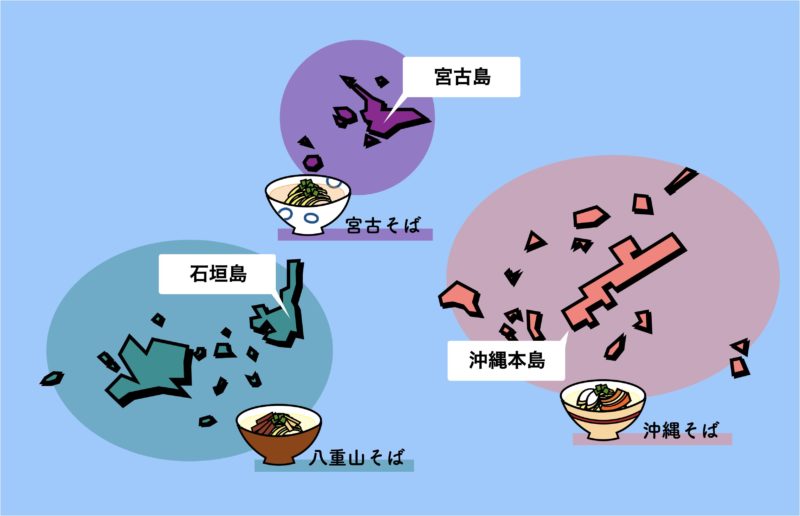
沖縄そばは、地域によって呼び方が変わります。
大きく分けると、次の3種類に分けることができます。
- 沖縄そば
- 宮古そば
- 八重山そば
沖縄そば
一般的に、沖縄本島地方で食べられるそばを「沖縄そば」と呼びます。
味は「とんこつ味」「かつおだし」の2種類、こってり系やあっさり系など種類が豊富。
宮古そば
宮古島地方で食べられるそばを「宮古そば」と呼びます。
味は「かつおだし」が中心で、三枚肉や島だこなどがトッピングされます。
八重山そば
石垣島地方(八重山地方)で食べられるそばを「八重山そば」と呼びます。
味は「かつおだし」が中心、牛やヤギがトッピングされたそばもあります。
沖縄そば|メニュー
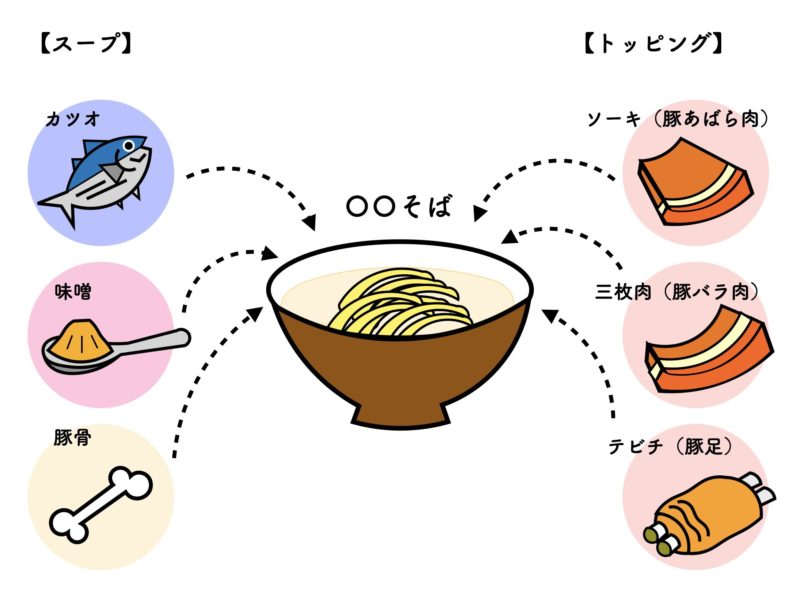
三枚肉そば
豚バラ肉の厚切りを煮込んだ「三枚肉」がトッピングされている沖縄そばです。
一般的な沖縄そばにトッピングされている具材。
ソーキそば
豚のあばら肉を柔らかく煮込んだ「ソーキ」がトッピングされている沖縄そばです。
醤油で炊き込むお店もあります。
テビチそば
豚の足を柔らかく煮込んだ「テビチ」がトッピングされた沖縄そばです。
味はさっぱりしたものが多く、コラーゲンが豊富。
なんこつそば
豚の軟骨を柔らかく煮込んだ「軟骨ソーキ」をトッピングした沖縄そばです。
トロトロに煮込まれており、コッテリした味が楽しめます。
沖縄そば|関連記事