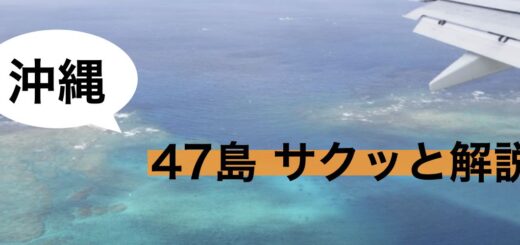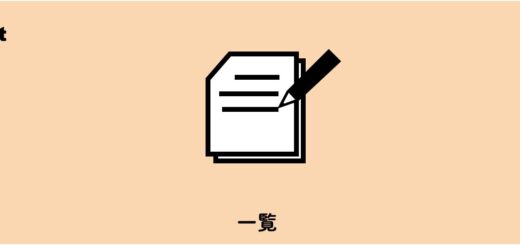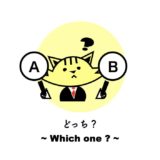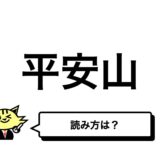【石垣島】宮良殿内|行き方・遊び方・周辺のお店
![]()
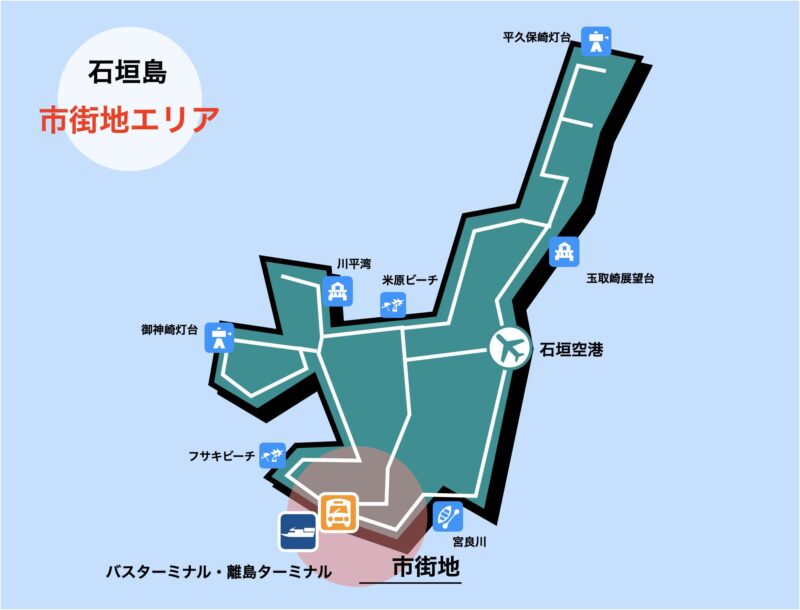
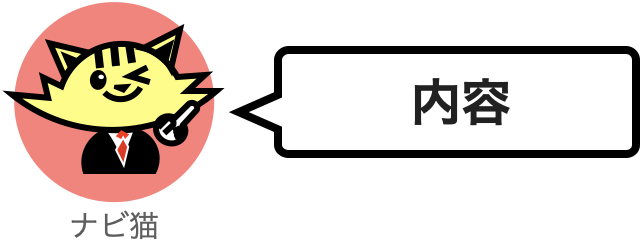
石垣島の宮良殿内(みやらどぅんち)について紹介している記事です
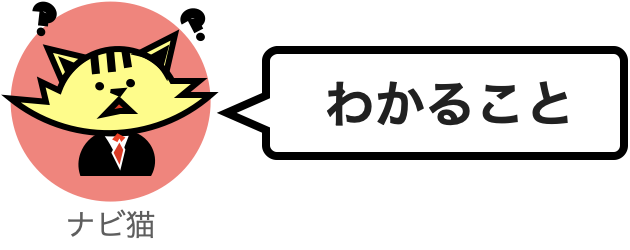
- 宮良殿内とは
- 宮良殿内への行き方
- 宮良殿内周辺のお店・スポット
目次
【石垣島】宮良殿内

| 所在地 | 沖縄県石垣市大川178 |
|---|---|
| 観光に必要な時間 | 20分〜 |
| 距離 | 空港から14km 港から1km |
| 最寄りバス停 | 「桟橋通り」から200m 「バスターミナル」から1km |
| バス路線 | 【東バス】系統10:空港線 |
| 駐車場 | なし |
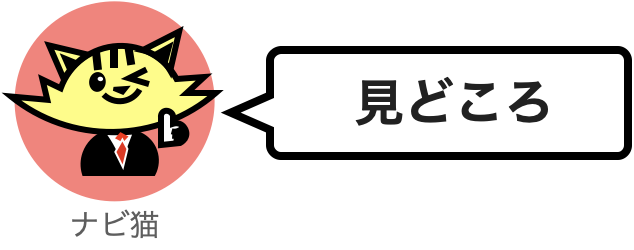
1800年代に建てられた住宅です。
赤瓦の建物、国の重要文化財に指定されています。
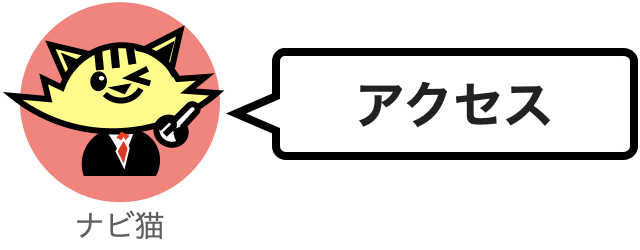
| レンタカー | |
|---|---|
| バス | |
| タクシー |
【石垣島】宮良殿内とは
宮良殿内は石垣島にある国の重要文化財です。
宮良殿内の読み方は「みやらどぅんち」。
琉球士族のお屋敷
1800年代に建てられた琉球士族のお屋敷、沖縄県に現存する数少ない瓦葺き住宅です。
庭を見学できる
庭の枯山水は国の名勝に指定され、観覧可能です(庭のみ観覧可:家の中に入ることはできません)。
【石垣島】宮良殿内|行き方
- 離島ターミナルから徒歩で10分
- 石垣空港から車で50分
※駐車場がないので、自転車もしくは徒歩でのアクセスがおすすめです
【石垣島】宮良殿内|周辺のお店

宮良殿内は、石垣島市街地のさんばし通り沿いにあります。
730交差点から徒歩5分
さんばし通りは730交差点から北東に行く通りです。
宮良殿内まで徒歩5分ほどですが、入口が分かりづらいので注意しましょう。
さよこの店が目印
宮良殿内への道は、「さよこの店」を目印にすると分かりやすいです。
飲食店やお店が多いエリア
飲食店、お土産屋の多いエリアです。
近くには、ユーグレナモールなどの商店街もあります。
宮良殿内周辺マップ
【石垣島】宮良殿内|関連記事
島から探す|関連記事