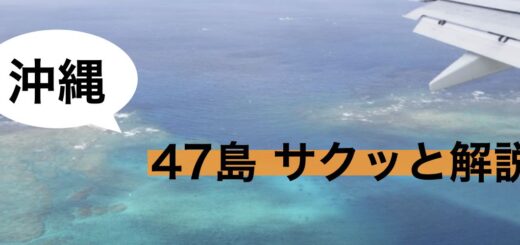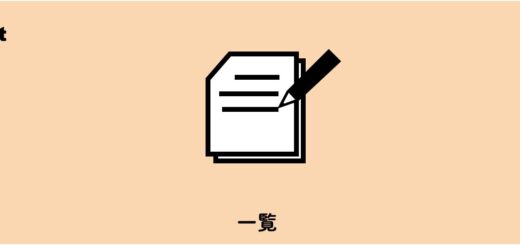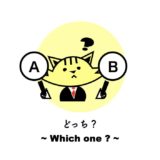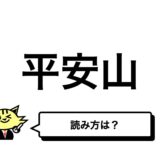琉球石灰岩
![]()
沖縄の石「琉球石灰岩」の紹介です。
琉球石灰岩

琉球石灰岩は、沖縄の石灰岩です。
さまざまな研究結果から、約50万年〜100万年前のものと推測されています。
首里城などの建築物や史跡に用いられ、古くから石垣や石畳の原料とされてきました。
琉球石灰岩とは
琉球石灰岩は、名前の通り沖縄にある石灰質の岩です。
沖縄本島の南部などには、琉球石灰岩でできた地盤があります。
琉球石灰岩|分布
琉球石灰岩の地盤は、沖縄県内全域に分布しています。
- 沖縄本島:「中部」「南部」
- 石垣島:「南側」
- 宮古島:「全域」に広く分布
琉球石灰岩|性質
琉球石灰岩の地盤は水を通しやすい性質があります。
そのため、地上は水はけがよい土地になります。
琉球石灰岩|鍾乳洞
石灰岩を通った水は、石灰質を含む水になります。
地下の形状などによっては、鍾乳洞を形成することもあります。
琉球石灰岩|用途
琉球石灰岩は、沖縄の建築に用いられます。
特に、「家の塀」や「石畳」に使うことが多いです。
琉球石灰岩|関連記事