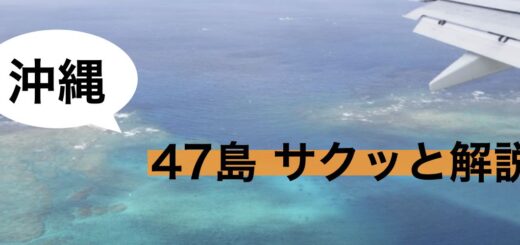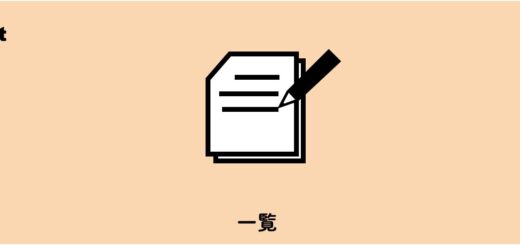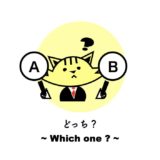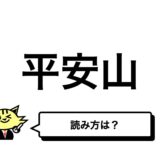フクギ
![]()
沖縄の植物「フクギ」の紹介です。
目次
フクギ
フクギは沖縄の街路樹や、家の防風林として利用されている木です。
枝を横に広げず、ほぼ垂直に上に伸ばすのが特徴。
葉がこんもりと丸く集まっているように見えます。
遠くから眺めると、マッチ棒のような形をしているので見分けやすい。
フクギの木

沖縄の住宅に植えられている木といえば、「フクギ」と言われるぐらい沖縄では有名な木です。
植物学的には常緑高木に分類される植物、樹高が高く、幹が太いのが特徴。
主に防風林となってくれるので、家に入ってくる風除けとして植えられています。
フクギの木|用途
フクギは沖縄の防風林として利用されてきた樹木です。
フクギに一旦、風、雨が当たることで、家に直接、雨風が当たるのを防いでくれる。
台風の時には、枝葉はバサバサ揺れますが、幹はしっかりとしており、とても頼もしい木です。
フクギ並木
離島では、集落内の主要な道路の道沿いに「フクギ」を植え、「フクギ並木」を作っている集落もあります。
風除け、潮風除けとして植えられていることが多いですが、夏には、日差し除けにもなってくれます。
沖縄本島の本部町にある「備瀬のフクギ並木」や、渡名喜島の「ふくぎ並木」が有名です。
フクギ|特徴

フクギの実
フクギの実は、3cmほどの大きさの「柿」みたいな形をしています。
夕方になると「ヤエヤマオオコウモリ」が飛んできて、一生懸命、実を食べている光景を見ることもできます。
フクギの葉
フクギの葉は対生で、タマゴ型の形をしています。
フクギの花
フクギは、5〜6月にクリーム色の小さな花を咲かせます。
道路に散った花を拾いあげると、香りが強く、ポプリのようないい香りがします。
フクギの樹皮
樹皮は染物の「染料」に使われます。
色味の深い「黄色」の染料として使われてきた歴史があります。
染料としてのフクギ
防風林、日除けの役割で植えられているフクギですが、樹皮は染料としても使われる植物です。
沖縄の染物「紅型」「琉球紬」「久米島紬」の色味の深い「黄色」にはフクギが使われています。
フラボン系の色素で染められる黄色は、なんとも色鮮やか。
伝統装束の染料に使うため、家の近くに植えられていることが多いです。
台風が通り過ぎると、樹皮が剥がれ落ちることもあり、剥がれ落ちた樹皮を使って染色します。
フクギ|関連記事
ブログ|関連記事